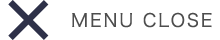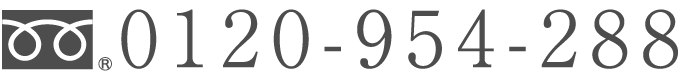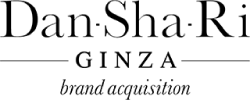ハイブランド買取物語5 グラフのジュエリー 八坂愛子の場合
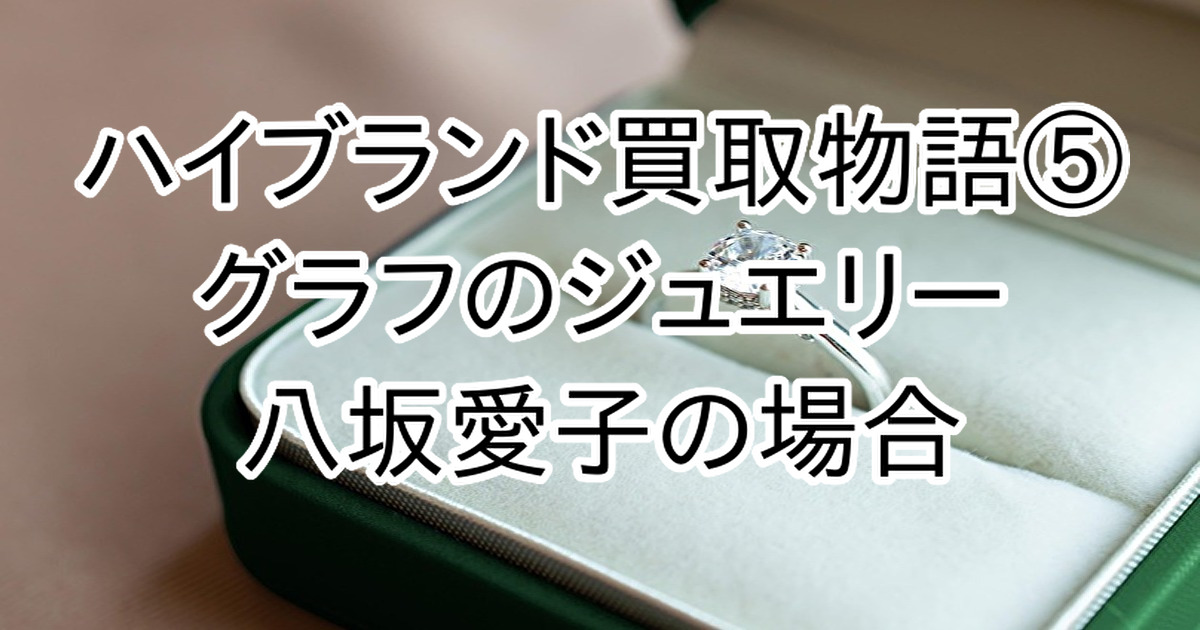
別れ
「海外転勤が決まった」
八坂愛子(仮名)はキッチンに立つとコップに水を注いだ。
煽るように飲み干すと、一言「そう」と呟いた。
相手の言わんとしていることは分かっている。
もう別れたいと言いたいのだ。
だったらきちんとこちらの目を見て「別れよう」と言えばいいのに。意気地のない男。
「じゃ、さよなら」
男が何か言おうとしていたが、荷物を家の外に放り出してやると名残惜しそうに何度も振り返りながらドアをくぐって去った。
なんだかとてもスッキリした。長年の重しがなくなったような。
八坂は閉め切っていたカーテンを開けた。
男がいる間はカーテンを閉めていなければならない。
窓から男の姿が見られてはいけないからだ。
男とは不倫関係だった。
結婚していると知っていて恋してしまったのだ。
しかし、それも始めのうちだけ。
最近では八坂の方から別れを切り出すか考えていたところだった。
つまり、ちょうどよかったのだ。
コップを置いて寝室に向かった。
男の私物を片付けるためだ。
もちろん、男の家に送ることはできない。すべて燃えるゴミとして処分する。
パジャマ、下着、歯ブラシ、ヘアワックスなどを、大きめのゴミ袋にどんどん放り込んでいった。
ゴミ袋が膨らむたびに、彼女の心は軽くなった。
処分に困るプレゼント

最後に処分に困ったのは、男から送られたプレゼントだった。
これから先も身につけられなくはないが、元彼のプレゼントを取っておくほど感傷的ではない。というか、手元に置いておきたくない。
かといってゴミ袋に放り込めるほど安物でもなさそうだ。
どうしようか考えた挙句、八坂はハイブランドの買取専門店に持ち込んだ。
フリマアプリで売却しようかとも思ったが、元彼の目に止まったらややこしいことになりそうだ。
誰にも知られずに売り払うなら、秘密を守ってくれそうなちゃんとしたお店だろうと思ったのだ。
はじめての査定

休日、銀座で遊ぶついでにDan-Sha-Ri(ダンシャリ)に寄った。
八坂は買取専門店など初めてだ。少し緊張したが、これが終われば現金が手に入るのだからと己を鼓舞してドアを開けた。
想像よりも落ちついた雰囲気の店内で、丁寧な接客を受ける。
案内された席に移動すると、彼女はカバンから袋を取り出した。
中から出てきたのはグラフのジュエリーだ。
ダイヤモンドがキラキラと輝くネックレスやイヤリング、指輪などが10点ほど転がり出てきた。
「すべて査定されますか」
店員に聞かれ、八坂は大きく頷いた。
全部売り払うために持ってきたのだから。
店員が丁寧かつ素早く査定を始めた。
手捌きは見ていて気持ち良い。
八坂はジュエリーがひとつひとつ手に取られるたびに、プレゼントされたその日のことを思い出していた。
まばゆい思い出

あのネックレスは付き合って1カ月記念にもらったもの。
「君にはもっと輝くものが似合う」なんて歯の浮くようなセリフと共にプレゼントしてくれた。はにかみながら受け取ったのを覚えている。
この指輪は誕生日のお祝いにもらった。
ダイヤがあんまり大きいものだから、どこにも着けていけなかったけど。
あっちのイヤリングは、ピアスの穴を開けると言ったときにもらった。
イヤリングでいいじゃない、と言いながら。
派手なものは着けられないと愚痴ったら、小さな一粒ダイヤのペンダントをくれたっけ。
それが、最後に査定された、あれだ。
何もかもが過去の思い出だ。
もうあの頃の初々しい自分もいなければ、愛を注いでくれた男もいない。
もっとも、男の愛は元々奥さんに向けられるべきものだったのだが。
それでも彼女にはすべてが今、優しく暖かな思い出として蘇ったのだった。
「査定額はこちらになります。いかがでしょうか」
店員の声にハッとする。
「はい。それでお願いします」
元々査定額がいくらであろうが売るつもりだった。だって、もういらないものなのだから。
好きな物に囲まれて

現金をその場で受け取り、店を後にした。
店に残してきたジュエリーと一緒に、過去の思い出も置いてきた。
八坂は銀座三越に向かう。
男が毛嫌いするので触れられなかったが、八坂はアートが好きなのだ。
現代アートを心ゆくまで堪能し、気になった作品をいくつか購入した。
どこに飾ろうか考えるだけでワクワクする。
八坂は購入した絵画を手に、ふと、信号待ちの合間に後ろを振り返った。
雑踏の中に男がいたような気がした。
信号が青に変わり、彼女は再び前を向き歩き出した。
彼女はもう振り返らなかった。
これから飾るアートのことで頭がいっぱいだったから。